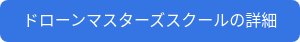「ドローンで空撮や点検の仕事をしたいけど、毎回飛行許可を取るのは大変そう…」「急な撮影依頼に対応できないかな?」あなたも今、そんな風に感じていませんか?そのお悩み、「包括申請」で解決できるかもしれません。この記事では、ドローン運用の手間を大幅に減らす包括申請について、制度の基本から具体的な申請の流れ、注意点まで、分かりやすく解説します。
目次
1-2. 包括申請:一定期間・範囲の飛行をまとめて申請する方法
2-2. メリット2:急な撮影依頼などビジネスチャンスに対応可能
4-2. 注意点2:飛行場所の制限(個別調整が必要な場合も)
1. ドローンの「包括申請」とは?個別申請との違い

ドローンをビジネスで活用する上で、避けて通れないのが航空法に基づく飛行許可・承認申請です。特に、人口集中地区での飛行や夜間飛行といった「特定飛行」を行う場合には、原則として国土交通大臣の許可・承認が必要となります。※1
この申請方法には、大きく分けて「個別申請」と「包括申請」の2種類があります。
1-1. 個別申請:一回ごとの飛行計画を申請する方法
個別申請は、その名の通り「いつ、どこで、どのような経路で」ドローンを飛行させるのか、一回一回の飛行計画を特定して申請する方法です。イベント空撮のように、日時と場所が完全に決まっている場合にはこの方法が用いられます。
しかし、点検や測量のように、天候や進捗によって飛行日時や場所が変動する業務の場合、その都度申請をやり直すのは非常に手間がかかります。
また趣味での飛行は、個別申請となります。
1-2. 包括申請:一定期間・範囲の飛行をまとめて申請する方法
そこで登場するのが「包括申請」※2です。
これは、同じ申請者が、一定の期間内に、特定の目的で、同じような条件の飛行を繰り返し行う場合に、それらの飛行をまとめて許可・承認してもらえる制度です。
例えば、「〇〇株式会社が、今後1年間、業務として日本全国で測量のために日中に目視外飛行を行う」といった形で申請します。これにより、一度許可を得れば、期間内はその都度申請することなく、条件の範囲内で柔軟にドローンを飛行させることが可能になります。
1-3. 【比較表】個別申請と包括申請の違い
|
項目 |
個別申請 |
包括申請 |
|
申請単位 |
飛行1回ごと |
一定期間・範囲をまとめて |
|
飛行計画 |
日時・場所・経路を特定 |
日時・場所を特定しない |
|
許可期間 |
計画した飛行期間のみ |
最長1年間 |
|
メリット |
どんな飛行内容でも申請可能 |
申請の手間を大幅に削減できる |
|
デメリット |
飛行の都度、申請が必要 |
申請できる条件が定められている |
|
向いている用途 |
イベント空撮、単発の依頼 |
定期的な点検、測量、報道取材 |
2. 手間削減だけじゃない!ドローン包括申請の3つのメリット

包括申請の最大の魅力は、やはり申請手続きの手間が省けることですが、メリットはそれだけではありません。ビジネスの観点から見ると、さらに大きな利点があります。
2-1. メリット1:申請手続きの手間と時間を大幅に削減
これは最も分かりやすいメリットです。個別申請の場合、飛行のたびに書類を作成し、申請・審査のプロセスを経る必要があります。審査には通常、数週間かかるため、計画から実行までのリードタイムが長くなってしまいます。
包括申請であれば、一度許可を取得すれば最長1年間は申請が不要になるため、事務的な負担が劇的に軽減されます。これにより、本来の業務であるドローンの操縦やデータ分析、顧客対応に集中できるようになります。
2-2. メリット2:急な撮影依頼などビジネスチャンスに対応可能
「明日、急に現場を見てほしい」といったクライアントからの突然の依頼。これはビジネスにおいて大きなチャンスです。しかし、個別申請では許可が間に合わず、機会を逃す可能性があります。
包括申請の許可があれば、条件の範囲内であれば即座に対応が可能です。「いつでも飛ばせる」という体制は、顧客からの信頼を高め、競合他社に対する大きな優位性となります。
2-3. メリット3:夜間や目視外など飛行の自由度が向上
ドローンビジネスの可能性は、日中・目視内の飛行だけにとどまりません。夜景の撮影、夜間の警備、広範囲の測量やインフラ点検における目視外飛行など、より高度な飛行技術が求められる場面は数多くあります。
これらの飛行はすべて許可・承認が必要な「特定飛行」に該当しますが、包括申請でこれらの飛行形態をあらかじめ許可・承認されておくことで、事業の幅を大きく広げることができます。
3. ドローン包括申請の基本的な流れ【DIPS 2.0対応】

では、実際に包括申請はどのように進めればよいのでしょうか。現在、申請は国土交通省のオンラインシステム「ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)」※3を通じて行うのが一般的です。ここでは、その基本的な流れを6つのステップで解説します。
3-1. ステップ1:事前準備(機体・操縦者情報の整理)
まず、申請に必要な情報を整理します。
- 機体情報: 飛行させるドローンの製造者、名称、型式、製造番号、そしてDIPS 2.0への機体登録後に発行される「登録記号」が必要です。
- 操縦者情報: 操縦者の氏名、住所、そしてこれまでの総飛行時間や、夜間・目視外といった申請したい飛行形態ごとの飛行経験(時間・回数)をまとめておきます。一般的に、各項目で10時間以上の飛行経験が求められます。
3-2. ステップ2:アカウント開設
DIPS 2.0を利用するために、まずはアカウントを作成します。メールアドレスや基本情報を入力して、個人または法人のアカウントを開設しましょう。
3-3. ステップ3:情報登録(機体・操縦者)
アカウントにログインしたら、「無人航空機情報の登録・変更」と「操縦者情報の登録・変更」メニューから、ステップ1で準備した情報をそれぞれ入力・登録します。ここで正確な情報を入力しておくことが、後の申請をスムーズに進めるポイントです。
3-4. ステップ4:飛行マニュアルの作成・添付
包括申請を行うには、安全な運航を担保するためのルールを定めた「飛行マニュアル」を添付する必要があります。これは、どのような体制で、どのような安全対策を講じて飛行させるかを文書化したものです。
一から作成するのは大変ですが、国土交通省が「航空局標準マニュアル」※1を公開しています。まずはこれをベースに、自身の運用体制に合わせて修正・追記していくのが効率的です。例えば、業務内容に応じた緊急連絡体制や、プライバシー保護に関する項目などを追加します。
3-5. ステップ5:申請書の作成・提出
いよいよ申請書の作成です。「飛行許可・承認申請」メニューから新規作成に進み、以下の主要項目を入力していきます。
- 申請の種類: 「期間・経路を特定しない申請(包括申請)」を選択。
- 飛行の目的: 「空撮」「測量」「インフラ点検」など、具体的な業務内容を選択。
- 飛行の期間: 最長で1年間。
- 飛行の範囲: 「日本全国」など。
- 飛行させる機体・操縦者: ステップ3で登録した情報を選択。
- 飛行形態: 夜間飛行、目視外飛行、人・物件との距離30m未満など、許可・承認を受けたい項目にチェックを入れます。
すべての入力が完了したら、ステップ4で作成した飛行マニュアルを添付し、申請を提出します。
3-6. ステップ6:審査・許可
申請が提出されると、国土交通省の審査官による内容の確認が始まります。書類に不備があったり、内容に疑問点があったりすると、DIPS 2.0を通じて補正指示(修正依頼)が来ます。これに迅速かつ的確に対応することが重要です。
特に、飛行経験や飛行マニュアルの内容について質問を受ける傾向があります。無事に審査を通過すると、DIPS 2.0上で「許可書(電子許可書)」が発行され、ダウンロードできるようになります。
4. ここに注意!包括申請を出す前に知っておきたい4つのポイント

包括申請は便利な制度ですが、飛行にあたってはいくつかの注意点があります。
4-1. 注意点1:有効期間は最長1年(更新が必要)
包括申請の許可・承認の有効期間は、原則として3ヶ月、最長でも1年間です。許可が切れれば、当然ながら特定飛行はできなくなります。継続して業務を行う場合は、期間が終了する前に必ず「更新申請」を行う必要があります。更新申請は、有効期間満了日のおおむね2ヶ月前から可能ですので、早めに準備を始めましょう。
4-2. 注意点2:飛行場所の制限(個別調整が必要な場合も)
「日本全国」で包括申請の許可を得ていても、それだけでは飛行できない場所があります。
- 空港周辺: 管轄の空港事務所との個別調整が必須です。
- 150m以上の上空: 管轄の管制機関との個別調整が必須です。
- イベント上空: 大勢の人が集まるイベント上空の飛行は、安全管理の観点から包括申請の対象外とされており、個別の許可申請が必要です。
- 私有地の上空: 土地の所有者や管理者の許可が別途必要です。
これらの場所で飛行する際は、包括申請とは別に、追加の手続きや調整が必要になることを覚えておきましょう。
4-3. 注意点3:飛行日誌の作成・携帯義務
2022年12月の航空法改正により、特定飛行を行う際には「飛行日誌」を作成し、飛行時に携帯することが義務付けられました。※4これは、いつ、どこで、誰が、どのような飛行を行い、点検や整備はいつ行ったかなどを記録するものです。
以前は「飛行実績報告」という形で定期的な報告義務がありましたが、現在は報告義務は廃止され、代わりに飛行日誌の作成・管理が求められています。この日誌は、万が一の事故の際の原因究明や、操縦者のスキル証明にも繋がる重要な書類です。
4-4. 注意点4:許可が出ない・取り消されるケース
申請すれば必ず許可が下りるわけではありません。
- 操縦者の飛行経験不足: 申請する飛行形態(例: 夜間飛行)に対して、十分な飛行実績(目安として10時間以上)がない場合。
- 機体の安全基準不適合: 安全装置(プロペラガードなど)が未装備であるなど、機体が安全に飛行できる状態でないと判断された場合。
また、許可取得後も、飛行マニュアルに記載した安全対策を遵守しなかったり、事故を起こしてしまったりした場合には、許可が取り消されることもあります。許可は安全運航を約束する「契約」のようなものだと心に留めておきましょう。
【セルフ申請用】
DIPS提出前チェックリスト 申請ボタンを押す前にもう一度!セルフ申請でよくある抜け漏れを防ぐための最終確認リストです。
|
□ 機体情報はDIPSに登録済みか?(登録記号は正しいか?) □ 操縦者情報はDIPSに登録済みか?(飛行時間は10時間以上か?) □ 飛行マニュアルは作成したか?(標準マニュアルを自身の体制に合わせ修正したか?) □ 飛行の目的、期間、範囲(日本全国など)は明確か? □ 申請したい特定飛行の項目(夜間飛行、目視外飛行など)に正しくチェックを入れたか? |
5. あなたはどっち?セルフ申請 vs 代理申請 徹底比較

ここまで包括申請の概要と流れを解説してきましたが、「思ったより大変そう…」と感じた方もいるかもしれません。包括申請には、自分で申請する「セルフ申請」の他に、行政書士などの専門家に依頼する「代理申請」という選択肢もあります。
どちらの方法があなたにとって最適か、一緒に考えてみましょう。
5-1. 代理申請という選択肢
「本業が忙しくて、申請書類を作成する時間がない」「DIPS 2.0の操作や専門用語が難しくて、自力でできるか不安だ」という方は、代理申請を検討する価値があります。
ドローン関連の申請を専門に扱う行政書士は、最新の法令や審査のポイントを熟知しています。複雑な飛行マニュアルの作成や、審査官とのやり取りも含めて任せることができるため、あなたは本来の業務に集中できます。
5-2. 【比較表】セルフ申請と代理申請
|
項目 |
セルフ申請 |
代理申請(行政書士など) |
|
費用 |
無料(申請手数料はかからない) |
数万円〜(専門家への報酬) |
|
時間・手間 |
かかる(情報収集、書類作成、DIPS操作など) |
かからない(専門家との打ち合わせ程度) |
|
確実性 |
△(不備があれば何度も修正が必要) |
◎(専門知識に基づき、スムーズな許可取得が期待できる) |
|
知識・ノウハウ |
◎(申請プロセスを通じて法令や手続きに詳しくなる) |
△(任せきりにすると、知識が身につきにくい) |
|
おすすめな人 |
・コストを最優先したい方 ・自分で挑戦して知識を身につけたい方 ・時間に余裕がある方 |
・本業に集中したい方 ・手続きの確実性を重視する法人 ・PC操作や書類作成が苦手な方 |
最終的にどちらを選ぶかは、あなたの状況次第です。コストを抑えたい、まずは自分でやってみたいという方はセルフ申請に挑戦する価値は十分にあります。一方で、時間と確実性を買うという意味では、代理申請は非常に有効な投資と言えるでしょう。
6. 包括申請はスタートライン!継続的なスキルアップと資格の重要性

包括申請の許可取得は、安全なドローン運用を始めるための第一歩です。まずは、許可取得後にやるべきことを確実に実施しましょう。
【許可が下りたら最初にやるべき3つのこと】
- 許可書のダウンロードと携帯 DIPS 2.0から発行される電子許可書(PDF)をダウンロードし、クラウドやスマートフォンなど、飛行時にいつでも提示できる場所に保管します。
- 飛行日誌の準備 特定飛行の際には飛行日誌の作成・携帯が義務付けられています。すぐに記録を始められるよう、国土交通省の様式を参考にフォーマットを準備しておきましょう。
- 個別調整先のリストアップ 許可証に「空港周辺や150m以上の上空を飛行する際には、別途調整を要する」といった条件が付いていないか確認します。該当する場合は、管轄の空港事務所や管制機関の連絡先をあらかじめリスト化しておくと、いざという時にスムーズです。
これらの準備を整えた上で、以下の心構えを持つことが重要です。 許可はあくまで「最低限のルールを守るための法的な手続き」です。しかし、実際の現場では、予期せぬ強風、GPSのロスト、機材トラブルなど、マニュアル通りにはいかない事態が起こり得ます。
そうした際に、安全に機体を帰還させて事故を防げるかどうかは、操縦者のスキルと経験に大きく左右されます。
包括申請で飛行の自由度が高まるからこそ、操縦者にはより一層の責任と技術が求められます。定期的にドローンスクールで訓練を受けたり、実践的な飛行経験を積んだりすることで、技術を常にアップデートしていくことが不可欠です。
また、2022年12月から始まったドローンの国家資格(一等・二等無人航空機操縦士)を取得することも、あなたの信頼性と技術力を客観的に証明する上で非常に有効です。
ドローンの技術は日進月歩です。包括申請をきっかけに、ぜひ継続的なスキルアップを目指し、より安全で価値の高いドローン活用を実現してください。
現場で役立つ専門技術を習得しませんか?
まとめ
ドローン包括申請は、申請の手間を省き、ビジネスチャンスを広げる強力なツールです。本記事で解説した流れと注意点を理解すれば、セルフ申請も十分に可能です。もし手続きに不安があれば、専門家への代理申請も有効な選択肢となります。あなたに合った方法で、安全なドローン運用を始めましょう。
ドローンマスターズスクールの詳細
■ドローンマスターズスクールの特徴や国家資格制度について、さらに詳しく知りたい方は当スクールの「無料説明会(ドローンセミナー)」に是非ご参加下さい!
ドローンマスターズスクール一覧
DMS茨城つくば校
DMS茨城笠間校
DMS埼玉浦和校
DMS栃木宇都宮校
DMS東京足立校
DMS千葉野田校(農薬散布ドローン専門)
DMS東京秋葉原校
参照・引用元一覧
- 国土交通省: 無人航空機の飛行許可・承認手続 - https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html - ドローン飛行に関する国の公式な手続き案内ページ。
- 国土交通省: 包括申請のご案内 - https://www.mlit.go.jp/koku/content/001490919.pdf - 国が発行する包括申請の公式な案内資料。
- 国土交通省: ドローン情報基盤システム2.0 - https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/ - 実際の申請を行うオンラインシステムの公式サイト。
- 国土交通省: 航空:飛行計画の通報・飛行日誌の作成 - https://www.mlit.go.jp/koku/operation.html - 2022年12月以降の飛行日誌義務化に関する公式情報。