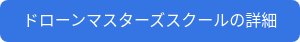ドローン飛行には様々な規制があり、場所や飛行方法によっては許可申請が必要です。
本記事では2025年の法改正に対応した最新情報と、申請簡略化のために役立つ資格取得について解説します。
目次
1.ドローン飛行で許可が必要なケース
ドローンを飛ばしたいと思ったとき、この場所で飛ばしても大丈夫なのか疑問に思ったことはありませんか?
実は、ドローンの飛行には航空法で定められた明確なルールがあり、場所や飛行方法によって国土交通大臣の許可や承認が必要になるケースがあります。
1-1.許可が必要な空域
航空法では、以下の空域でドローンを飛行させる場合、飛行前に許可を得る必要があります。
- 空港等の周辺空域:空港やヘリポートの周辺では、有人航空機の離着陸に影響を与える可能性があるため、飛行には許可が必要です。
- 地表または水面から150m以上の高さの空域:高度の高い場所での飛行は有人航空機との衝突リスクがあります。
- 人口集中地区(DID)の上空:人口密度が高い地域では、落下時の危険性が高まるため規制されています。
- 緊急用務空域:災害発生時などに指定される空域です。※原則飛行禁止
人口集中地区の確認は、国土地理院の地図サービスで確認できます。赤色で示された区域が該当エリアになります。
参考:
- 国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html - 国土地理院「地理院地図」(人口集中地区の確認)
https://maps.gsi.go.jp/
1-2.許可が必要な飛行方法
飛行場所だけでなく、以下の飛行方法でドローンを操縦する場合にも、事前に承認が必要です。
- 夜間飛行:日没から日の出までの飛行
- 目視外飛行:操縦者が直接目視できない状態での飛行
- 人や物件から30m未満の距離での飛行:接近飛行による事故リスクが高まるため
- イベント上空での飛行:多くの人が集まる催し物の上空
- 危険物の輸送:火薬類、高圧ガス、毒物など
- 物件投下:空中からものを落とす行為(農薬散布や種まきなども含む)
「ドローンを飛ばすだけなのに、これほど規制があるの?」と感じるかもしれませんが、これらの規制は安全を確保するために必要なものです。特に、初めてドローンを飛ばす方は、まずは規制のない場所で練習することをおすすめします。
1-3.無許可飛行のリスクと罰則
許可が必要な空域や飛行方法で無許可飛行を行うと、思わぬトラブルや厳しい罰則に直面する可能性があります。「少しだけなら」という軽い気持ちが大きなリスクにつながることを理解しましょう。
航空法では、無許可飛行に対して50万円以下の罰金が科される可能性があります。特に以下のような違反が罰則の対象となります。
- 人口集中地区や空港周辺などの規制区域での無許可飛行
- 夜間や目視外など、特定の飛行方法での無許可飛行
- 国土交通大臣の指示に従わなかった場合(1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
近年の取締り強化により、実際に罰金を科された事例も増えています。
特にSNSに投稿した飛行映像から後日摘発されるケースもあるため注意が必要です。
さらに、無許可飛行中に事故が発生した場合、民事上の損害賠償責任も発生します。事故の規模によっては数千万円の賠償責任を負う可能性もあり、無許可飛行では保険が適用されないケースもあります。
「小型無人機等飛行禁止法」による重要施設周辺の飛行禁止区域や、地方自治体の条例による規制にも注意が必要です。これらに違反した場合も、別途罰則が科される可能性があります。
参考:
- 国土交通省「無人航空機の飛行ルール」
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html - 警察庁「小型無人機等飛行禁止法」の解説 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
2.ドローン飛行許可の申請方法

「申請が必要だとわかっても、具体的にどうやって申請するの?」という疑問にお答えします。
ドローンの飛行許可・承認申請は、2025年現在、基本的にオンラインサービス「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」を通じて行います。
2-1.DIPS2.0での申請手順
- アカウント作成とログイン:初めて利用する場合は、DIPS2.0のサイトでアカウントを作成します。機体登録で取得したIDとパスワードでログインできます。
- 無人航空機情報と操縦者情報の登録:申請の前に、使用する機体と操縦者の情報を登録しておく必要があります。
- 申請書の作成:飛行の目的、日時、経路、高度、安全管理のための措置などを入力します。
- 申請書の提出:作成した申請書を、管轄の航空局または空港事務所に提出します。
- 審査と許可書の発行:審査が完了すると、許可書または承認書が発行されます。
2025年3月24日からDIPS2.0は大幅に改修され、申請手続きが簡素化されました。特に飛行させる無人航空機の追加基準への適合性の登録方法が変更され、申請の都度追加基準の登録を行う方式から、事前登録をする方式に変わっています。
審査には一定の期間を要するため、飛行開始予定日の10開庁日(土日・祝日を除く)以上前に申請することが推奨されています。しかし、実際には申請内容に不備があると追加確認に時間がかかるため、3〜4週間程度の余裕を持って申請するのが安心です。
2-2.申請時の注意点
申請時によくある間違いを避けるためのポイントをいくつかご紹介します。
- 申請先の誤り:空港周辺や150m以上の高さでの飛行は東京空港事務所長または関西空港事務所長宛てに、それ以外は管轄の航空局長宛てに申請します。
- 申請書の不備:必要事項の未記入や添付資料の不足が多いため、提出前の確認が重要です。
- 他の規制の確認:航空法以外にも、「小型無人機等の飛行禁止法」や地方公共団体の条例による規制もあるため、事前確認が必要です。
「申請書の作成って複雑そう...」と感じる方も多いですが、国土交通省の「飛行許可・承認申請ポータルサイト」では、申請方法を動画で解説しており、初めての方でもわかりやすく解説されています。
参考:
- 飛行許可・承認申請ポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/koku/permitapproval/ - ドローン情報基盤システム操作マニュアル
https://www.mlit.go.jp/common/001876691.pdf
3.許可申請を簡略化する資格取得のメリット
実は、適切な資格を取得することで、申請手続きを大幅に簡略化できる場合があります。
3-1.体認証と技能証明の組み合わせによる簡略化
2025年3月の審査要領改正により、カテゴリーⅡ飛行の一部については、以下の条件を満たすことで許可・承認申請が不要になりました:
- 立入管理措置を講じること:第三者が立ち入らないよう適切な措置を取る
- 技能証明を持つ操縦者が飛行させること:国家資格を取得した操縦者であること
- 機体認証を受けたドローンを使用すること:安全基準を満たした認証機体であること
- 飛行マニュアルを作成すること:安全確保のための措置を文書化すること※国土交通省作成の飛行マニュアル使用も可能
特に注意したいのは、「型式認証」と「機体認証」の違いです。単に型式認証を取得しただけでは「機体認証無人航空機」とはならないため、申請簡略化の恩恵を受けることができません。
3-2.国家資格の種類と取得方法
ドローンの国家資格には、一等と二等の技能証明があります。
- 一等無人航空機操縦士:カテゴリーⅢ飛行(第三者上空での飛行)が可能
- 二等無人航空機操縦士:カテゴリーⅡ飛行での申請簡略化が可能
これらの資格は、国土交通省の登録講習機関で取得できます。「資格取得は難しそう...」と思われるかもしれませんが、ドローンマスターズスクールをはじめとする専門スクールでは、初心者から丁寧に指導してくれるため安心です。
一般的に、二等技能証明の取得には10〜25万円程度の費用と、数日から1週間程度の講習期間が必要です。一見高額に感じるかもしれませんが、繰り返し申請する手間と時間を考えると、長期的には効率的な投資と言えるでしょう。
3-3.ドローンマスターズスクールの資格取得コース
ドローンマスターズスクールでは、国家資格の取得に対応したコースを提供しています。
特に以下のような特徴があります。
- 国家資格コース:無人航空機操縦士の技能証明取得を目指すコース
- 完全アフターフォロー型:卒業後も無料で操縦訓練を受けられるサポート体制
- 実践的なカリキュラム:実際の現場で役立つ技術を習得できる内容
4.業種別・目的別の許可申請ポイント

ドローンの活用方法は業種や目的によって大きく異なります。
ここでは、代表的な利用シーンごとの申請ポイントを解説します。
4-1.空撮・映像制作の場合
風景や建物を撮影する目的でドローンを使う場合、以下の点に注意が必要です:
- 撮影場所の確認:市街地(人口集中地区)での撮影には許可が必要。飛行方法によっては目視外飛行にもなるため目視外飛行の許可が必要。
- プライバシーへの配慮:住宅地近くでの撮影は、プライバシー侵害に注意
- 被写体の権利:建物や施設の撮影は、管理者の許可が必要な場合も
「素晴らしい映像を撮りたい」という気持ちは理解できますが、法的な問題だけでなく、周囲への配慮も重要です。特に初めての場所で撮影する際は、事前の現地確認と関係者への説明を心がけましょう。
4-2.農業用ドローンの場合
農薬散布や種まきなどに使用する場合、以下の点に注意します:
- 物件投下に該当:農薬散布は「物件投下」に該当するため許可が必要
- 農林水産航空協会の基準:安全対策や散布基準に準拠する必要がある
- 使用する薬剤の確認:農薬取締法に基づく適正使用
農業用ドローンの場合、国土交通省だけでなく農林水産省の規制も関わってくるため、複数の法令を確認する必要があります。「複雑すぎてわからない...」という場合は、農業ドローン専門のスクールや講習を受けることをおすすめします。
4-3.点検・測量の場合
インフラ点検や測量にドローンを使用する場合は、以下の点がポイントです:
- 目視外飛行への対応:橋梁の下部や建物の裏側など、操縦者から見えない場所の点検には目視外飛行の承認が必要
- 飛行の安全性確保:風の影響を受けやすい高所や構造物近くでの飛行には、特に安全対策が重要
- データの精度と信頼性:測量結果を公的に使用する場合、機器の精度や操作の正確性が求められる
点検・測量の現場では、「安全」と「精度」の両立が求められます。
そのためには、専門的な技術と知識を持った操縦者が必要です。資格取得だけでなく、実務経験を積むことも重要です。
参考:
- 農林水産航空協会「無人航空機による農薬散布等について」
http://www.j3a.or.jp/ - 国土交通省「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会 とりまとめ」
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001478581.pdf
5.2025年法改正で変わったこと
2025年3月24日から施行された審査要領の改正により、ドローンの飛行許可・承認手続きは大きく変わりました。最新の変更点を理解しておくことで、スムーズな申請が可能になります。
5-1.審査要領改正のポイント
今回の改正では、主に以下のような変更が行われました:
- 申請手続きの簡素化:機体と操縦者の基本基準/追加基準への適合性を申請者自身が確認する方式に変更
- 書式の変更:申請書や別添資料の書式が変更され、より記入しやすく
- 審査の迅速化:申請者自己確認方式への移行により、審査期間の短縮が期待される
「これまでの申請書は使えないの?」という疑問をお持ちの方も多いですが、2025年3月24日以降は旧書式を使用した申請はできなくなりました。既に取得している許可・承認の更新や変更も、新書式での新規申請が必要です。
5-2.機体登録制度の更新期限
もう一つ注意すべき点は、機体登録の更新期限です。2025年6月19日が最初の登録更新期限となっており、期限切れにならないよう注意が必要です。更新を忘れると再登録とリモートID搭載が必要になる可能性もあります。
「登録したことは覚えているけど、いつ更新すればいいの?」という方は、DIPS2.0にログインして登録情報を確認しましょう。機体ごとに登録日から3年間が有効期間となっています。
6.まとめ
ドローン飛行の許可申請は複雑に見えますが、適切な知識と資格があれば手続きは簡略化できます。最新の法改正情報を把握し、安全で合法的な飛行を心がけましょう。無許可飛行のリスクを理解し、必要な手続きを確実に行うことが重要です。
ドローンマスターズスクールの詳細

■ドローンマスターズスクールの特徴や国家資格制度について、さらに詳しく知りたい方は当スクールの「無料説明会(ドローンセミナー)」に是非ご参加下さい!
ドローンマスターズスクール一覧
DMS茨城つくば校
DMS茨城笠間校
DMS埼玉浦和校
DMS栃木宇都宮校
DMS東京足立校
DMS千葉野田校(農薬散布ドローン専門)
DMS東京秋葉原校