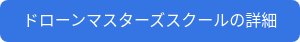ドローン技術の進化と普及に伴い、空撮や点検、測量など様々な場面でドローンが活用されています。
しかし、安全な空域利用のためには適切な申請手続きが必要です。
本記事では、ドローン飛行申請の基礎から実践まで解説します。
目次
-
1-1. 場所による申請要件
1-2. 飛行方法による申請要件
-
2-1. 個別申請と包括申請の違い
2-2. カテゴリー別の申請方法
-
3-1. DIPS2.0アカウントの作成
3-2. 機体情報と操縦者情報の登録
3-3. 申請書の作成と提出
3-4. 審査と許可書の取得
-
4-1. 基本的な必要書類
4-2. 航空局標準マニュアルの活用法
4-3. 機体認証・操縦者技能証明による簡略化
-
5-3. 包括申請の代行サービス
-
6-1. 飛行計画の通報
6-2. 飛行日誌の作成と保管
6-3. 事故発生時の報告義務
6-4. 申請内容に変更があった場合の対応
1.ドローン飛行申請が必要なケースを徹底解説
ドローンを飛行させる際、どのような場合に申請が必要になるのでしょうか。
航空法に基づき、以下のケースでは国土交通省への申請が必須となります。
1-1. 場所による申請要件
国土交通省の規定によると、以下の空域でドローンを飛行させる場合には許可申請が必要です。
- 空港等の周辺の上空:航空機の離着陸に影響を与える可能性がある空域
- 人口集中地区(DID)の上空:人口密度が高い市街地上空
- 地表または水面から150m以上の高さの空域:高高度での飛行
これらの空域は、航空機の運航や地上の人々の安全に直接関わるため、厳格な管理が求められています。
「DIDって何?自分の住んでいる場所が該当するかどうか分からない...」という方も多いのではないでしょうか。DID(人口集中地区)は総務省統計局が定める区域で、地理院地図で確認することができます。
1-2. 飛行方法による申請要件
場所だけでなく、以下の飛行方法でドローンを操作する場合も承認申請が必要です:
- 夜間飛行:日没から日の出までの時間帯の飛行
- 目視外飛行:操縦者が直接ドローンを視認できない状態での飛行
- 30m未満の距離での第三者上空飛行:人や物との間隔が30m未満での飛行
- 物件投下:ドローンから物を落とす飛行
- 危険物輸送:火薬類や高圧ガスなどの危険物を運搬する飛行
- 催し場所の上空飛行:イベント、大会などの主催者がいて、人が多く集まる場所
これらの飛行方法は、通常よりもリスクが高いと判断されるため、適切な安全対策が講じられているかを確認するプロセスが必要となります。
「どの程度から夜間飛行に該当するの?」という疑問も多いでしょう。
航空法上の夜間とは、日没から日の出までの時間を指します。時期や地域によって異なるため、気象庁の日の出・日の入りデータを確認することをおすすめします。
参考:
- 国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」 - https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
2.ドローン飛行申請の種類と選び方

ドローンの飛行申請には、「個別申請」と「包括申請」の2種類があります。
それぞれの特徴を理解して、自分の飛行計画に合った申請方法を選びましょう。
2-1.個別申請と包括申請の違い
個別申請は、特定の日時や場所での単発的な飛行や危険度の高い飛行など。
例えば、イベントでの空撮や一度きりの点検作業や空港周辺、150m以上飛行などがこれに該当します。個別申請の特徴は以下の通りです:
- 特定の日時・場所を指定して申請
- 飛行ごとに申請が必要
- 申請内容の変更が難しい
- 飛行場所の管理者(空港管理者やイベント主催者など)と事前打ち合わせをした後に飛行申請をする
一方、包括申請は同じ条件で繰り返し飛行する場合や、広範囲での飛行計画がある場合に適しています。
包括申請には以下の特徴があります。
- 最長1年間の期間で申請可能
- 全国または特定地域での反復飛行が可能
- 天候不良時の日程変更に柔軟に対応できる
- 一度の申請で複数回の飛行が可能
2-2.カテゴリー別の申請方法
2022年の航空法改正により、ドローンの飛行形態はリスクに応じて3つのカテゴリーに分類されるようになりました:
カテゴリーⅠ:特定飛行に該当しない飛行(申請不要)
カテゴリーⅡ:立入管理措置を講じた上での特定飛行(条件により申請が必要な場合と不要な場合がある)
カテゴリーⅢ:第三者上空での特定飛行(厳格な審査による申請が必要)
特に注目すべきは、カテゴリーⅡの中でも「機体認証を受けた無人航空機」を「操縦者技能証明を持つ者」が飛行させる場合は、一部の特定飛行(DID上空、夜間、目視外、30m未満の飛行)について申請が不要になる点です。ただし、空港周辺や150m以上の高さでの飛行、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、25kg以上の機体の飛行については、技能証明や機体認証の有無にかかわらず個別に許可・承認が必要です。
「自分の飛行計画はどのカテゴリーに該当するの?」という疑問には、国土交通省が提供する「飛行カテゴリー決定のフロー図」が参考になります。
3.DIPS2.0での申請手続きステップバイステップガイド
ドローンの飛行許可・承認申請は、国土交通省の「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」を通じて行います。ここでは、申請の具体的な流れを解説します。
3-1. DIPS2.0アカウントの作成
まず最初に、DIPS2.0のアカウントを作成する必要があります。以下の手順で進めましょう。
- DIPS2.0ポータルサイトにアクセス
- 「新規登録」ボタンをクリック
- 個人または企業・団体のいずれかを選択(業務利用の場合は「企業・団体」を選択)
- 必要事項を入力し、メールアドレスを登録
- 送信されたメールのリンクからパスワードを設定
企業として申請する場合は、個人ではなく必ず「企業・団体」としてアカウントを開設してください。個人アカウントでは企業名等の入力ができないため注意が必要です。
3-2. 機体情報と操縦者情報の登録
申請の前に、飛行させるドローンの機体情報と操縦者の情報を登録します。
- DIPS2.0にログイン
- 「無人航空機情報」から機体の登録・更新
- 「操縦者情報」から操縦者の登録・更新
2025年3月の審査要領改正に伴い、操縦者の基本基準・追加基準への適合性は「操縦者情報の更新」から一括登録する方式に変更されました。申請前に必ず操縦者情報の更新を行いましょう。
3-3. 申請書の作成と提出
機体と操縦者の情報を登録したら、以下の手順で申請書を作成します。
- 「飛行許可・承認申請」メニューから「新規申請」を選択
- 必要事項を入力(飛行の目的、日時、場所、高度など)
- 飛行マニュアルなど必要書類をアップロード
- 入力内容を確認し、申請を提出
申請先の選択を間違えると補正指示が発生する事例が多いため注意が必要です。
空港等周辺、緊急用務空域、150m以上の高さの空域を飛行させる場合は東京空港事務所長または関西空港事務所長宛てに、それ以外の場合は飛行場所を管轄する東京航空局長または大阪航空局長宛てに申請します。
3-4. 審査と許可書の取得
申請が受理されると審査が行われ、問題がなければ許可・承認が下ります。
- 申請状況はDIPS2.0の「申請一覧」から確認可能
- 審査中に追加の情報を求められる場合は「補正指示」に従って対応
- 許可・承認が下りると、DIPS2.0内で許可書を確認可能
- 紙面での許可書発行を希望した場合は、申請先に返信用封筒を送付
審査には一定の期間を要するため、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日・祝日を除く)には申請書類を提出しましょう。
申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要するため、余裕を持って3〜4週間前には申請することをおすすめします。
参考:
- 国土交通省「ドローン情報基盤システム操作マニュアル(飛行許可・承認申請編)」 - https://www.mlit.go.jp/common/001876691.pdf
4.申請に必要な書類と準備ポイント
ドローン飛行申請を円滑に進めるためには、必要書類を適切に準備することが重要です。
ここでは、申請に必要な主な書類とその作成ポイントを解説します。
4-1.基本的な必要書類
DIPS2.0での申請に必要な基本的な書類は以下の通りです:
- 申請書:DIPS2.0上で入力する基本情報
- 飛行マニュアル:安全な飛行のための手順や対応策をまとめた文書
- 無人航空機の機能・性能に関する基準への適合性を証明する書類:機体の性能や安全機能に関する情報
- 無人航空機を飛行させる者の飛行経歴・知識・能力を証明する書類:操縦者の技能や経験に関する情報
- 飛行の場所を示す地図:飛行エリアを明示した地図情報(個別申請の場合)
特に初めての申請では、書類作成に手間取ることが多いため、国土交通省が公開している「航空局標準マニュアル」を活用するのがおすすめです。このマニュアルをベースに自社の運用に合わせてカスタマイズすることで、効率的に書類を準備できます。
4-2.航空局標準マニュアルの活用法
航空局標準マニュアルは、基本的な飛行マニュアルのテンプレートとして利用できます。このマニュアルを使用する際のポイントは以下の通りです:
- マニュアル内の記載事項を確認し、自社の運用体制に合わせて修正
- 特に安全管理体制や緊急時の対応方法は具体的に記載
- 飛行する無人航空機の仕様や特性に合わせた内容に調整
- 飛行させる場所や方法に応じた安全対策を追記
2025年3月に航空局標準マニュアルが改正されましたので、最新版を確認することが重要です。マニュアルの内容を十分に理解した上で活用しましょう。
4-3.機体認証・操縦者技能証明による簡略化
2022年12月の航空法改正により、機体認証を受けた無人航空機または型式認証無人航空機を使用して特定飛行の許可・承認申請を行う際は、一部資料の添付を省略できるようになりました。
例えば、機体認証を受けた無人航空機を使用する場合、「無人航空機の機能・性能に関する基準への適合性を証明する書類」の添付が不要になります。
また、操縦者技能証明を持つ者が飛行させる場合は、「無人航空機を飛行させる者の飛行経歴・知識・能力を証明する書類」の添付が省略できます。
ただし、注意が必要なのは、「型式認証の取得のみでは機体認証無人航空機とはならない」という点です。カテゴリーⅡの飛行において申請を不要とするためには、型式認証だけでなく機体認証の取得が必要となります。
参考:
- 国土交通省「航空局標準マニュアル」 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html#anc03
5.専門家によるドローン申請サポートサービスのご案内

ドローン飛行申請の手続きは、初めての方にとって複雑で時間がかかることがあります。
専門家のサポートを利用することで、効率的かつ確実に申請手続きを進めることができます。
5-1.申請手続きの難しさと専門家サポートのメリット
ドローン飛行申請には、以下のような難しさがあります。
- 複雑な法規制や申請要件の理解が必要
- 適切な書類作成には専門知識が求められる
- 申請内容の不備により審査が長引くリスク
- 法改正に伴う最新の申請要件への対応
こうした課題を解決するため、専門家による申請サポートサービスの利用が効果的です。
専門家サポートのメリットには以下のようなものがあります。
- 経験豊富な専門家による確実な申請手続き
- 申請書類の作成から提出までのワンストップサポート
- 審査機関とのやり取りを代行
- 法改正や制度変更への迅速な対応
- 申請の承認率向上と審査期間の短縮
5-2.ドローンマスターズスクールの申請サポートサービス
ドローンマスターズスクールでは、ドローン飛行申請をサポートするサービスを提供しています。
経験豊富なインストラクターが、申請書類の作成から提出までをトータルでサポートします。
特に初めての申請や複雑な飛行計画の場合、専門家のサポートを受けることで、スムーズに許可・承認を取得できる可能性が高まります。また、国家資格取得コースと組み合わせることで、操縦技術の向上と合わせて申請手続きのノウハウも習得できます。
ドローンマスターズスクールの申請サポートサービスについて詳しく知りたい方は、
ドローンマスターズスクール一覧ページをご覧いただくか、お問い合わせページからお気軽にご相談ください。
5-3.包括申請の代行サービス
包括申請はその特性上、より複雑な手続きが必要となることがありますが、行政書士などの専門家に依頼することで、申請手続きの負担を大幅に軽減できます。
包括申請代行サービスの費用相場は、一般的に22,000円から39,000円程度とされています。サービス内容や申請内容の複雑さによって料金は変動しますが、時間と手間を考えると専門家への依頼が効率的な選択肢となることが多いです。
「自分で申請するか、代行サービスを利用するか」の判断は、申請の複雑さ、自社のリソース状況、申請の緊急性などを考慮して決めることをおすすめします。
6.申請後の義務と注意点
ドローン飛行の許可・承認を取得した後も、安全な運用のために遵守すべき義務があります。ここでは、申請後に求められる主な義務と注意点を解説します。
6-1.飛行計画の通報
特定飛行を行う場合は、原則として飛行の24時間前までに飛行計画を通報する必要があります。
飛行計画の通報は、DIPS2.0の「飛行計画登録」機能を利用して行います。
通報すべき内容には以下が含まれます。
- 飛行日時
- 飛行場所
- 飛行高度
- 機体情報
- 操縦者情報
- 連絡先
飛行計画の通報は、航空機との安全な空域共有のために重要な手続きです。確実に実施しましょう。
6-2.飛行日誌の作成と保管
2022年12月の法改正により、飛行実績の報告義務は廃止されましたが、代わりに飛行日誌の作成・保管が義務付けられました。飛行日誌には以下の内容を記録します。
- 飛行年月日
- 飛行させた無人航空機の登録記号又は試験飛行届出番号
- 飛行させた無人航空機を飛行させた者の氏名
- 離陸場所及び離陸時刻
- 着陸場所及び着陸時刻
- 飛行時間
- 飛行の概要
- 飛行中の故障、トラブル等の有無及び発生時の対応措置
- 無人航空機の点検・整備記録
飛行日誌は、飛行させた日から2年間保存する必要があります。国土交通省から提出を求められた場合には、速やかに提出できるよう適切に管理しましょう。
6-3.事故発生時の報告義務
ドローンの飛行中に事故が発生した場合、直ちに国土交通省航空局に報告する義務があります。報告が必要なケースは以下の通りです。
- 人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失または航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合
- 飛行させている無人航空機の制御不能又は不時着を発生させた場合
- 飛行中の無人航空機が発火した場合
事故報告は、国土交通省のWebサイトにある専用フォームから行います。
報告の遅れや怠りは法令違反となる可能性があるため、事故発生時は速やかに対応しましょう。
6-4.申請内容に変更があった場合の対応
申請内容に変更が生じた場合は、変更内容に応じた手続きが必要です。主な変更ケースと対応は以下の通りです。
- 機体の追加: 変更申請が必要
- 操縦者の追加: 変更申請が必要
- 飛行範囲の拡大: 変更申請が必要
- 飛行期間の延長: 更新申請が必要
- 申請者情報の変更: 変更届の提出が必要
変更申請は、原則として元の申請と同じ手続きを行います。申請内容の変更を計画する場合は、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることをおすすめします。
参考:
- 国土交通省「無人航空機の飛行」
https://www.mlit.go.jp/koku/operation.html
7.まとめ
ドローン飛行申請は適切な準備と手続きが重要です。
申請が必要なケースを理解し、DIPS2.0を活用した効率的な申請を心がけましょう。
ドローンマスターズスクールの詳細
■ドローンマスターズスクールの特徴や国家資格制度について、さらに詳しく知りたい方は当スクールの「無料説明会(ドローンセミナー)」に是非ご参加下さい!
ドローンマスターズスクール一覧
DMS茨城つくば校
DMS茨城笠間校
DMS埼玉浦和校
DMS栃木宇都宮校
DMS東京足立校
DMS千葉野田校(農薬散布ドローン専門)
DMS東京秋葉原校